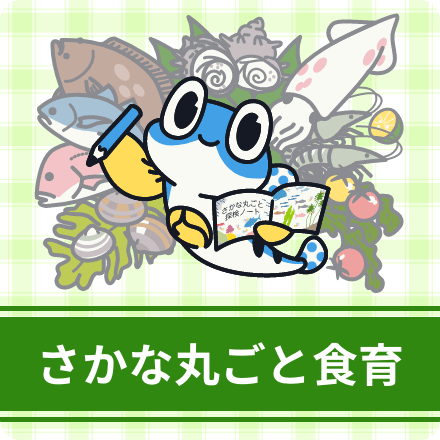朝潮運河いきものルネサンス
マハゼを釣りに行こう~船でハゼ釣り
2021.04.1今まで、ハゼ釣りの入門ということで、川岸や運河沿い、海辺でのハゼ釣りを前提にお話をしてきました。今回は、その発展形である船に乗ってのハゼ釣り(船釣り)について、お話しします。
船に乗ってハゼを釣る理由のひとつは、ハゼのいるポイントに近づきたいということです。ですから、どこで、どんなハゼを釣りたいか?によって、選ぶ船が変わります。
水深が50cmから1m程度の浅場に集まるデキハゼ(当年生まれの小型のハゼ)をねらうのであれば、できるだけ小回りが利いて、喫水(きっすい:水中に沈んでいる深さ)の浅い手こぎボートを用いるボート釣りが最適です。貸しボート屋さんによっては、ポイント近くまで動力船で連れて行ってくれることも有りますので楽ちんです。

江戸川でのボート釣り風景(動力船で釣り場へ)
ポイントに着いたら、流れに舳先(へさき:船の前の方)を向けて、アンカーを入れて船を固定します。流れや風によってボートはふれ回ることになりますので、近くの船や障害物などにぶつからない様、十分に間をあけることが大切です。また、アンカーを入れることで、ポイントの水深を確認することもできます。アンカーを少し引っ張ると、その感覚で底の状態が砂なのか、どろなのか、障害物はどの程度ありそうかということもわかります。ボート釣りには、そうした海底の様子や潮、天気などに合わせてポイントを探るという楽しみもあります。

江戸川でのボート釣り風景(手こぎボートでの釣り)
港や入江など囲われた場所であれば、こうした小型の手こぎボートでも十分に楽しむことができますが、大型のハゼ(落ちハゼ)をねらうには、運河沿いで、流れに沿ってある程度広い場所を探りながら釣る、練り船(ねりぶね)がおすすめです。船長さんが船を流れに合わせてたくみに操り、運河沿いのポイントを探ります。今は少なくなってしまいましたが、櫓(ろ)で船を操り、運河をゆったりと流れながらハゼを釣るのは、伝統ある江戸前ハゼ釣りの真骨頂です。中通しの和竿などを使うと、さらに趣(おもむき)があるばかりでなく、落ちハゼのわずかなあたりを感じることができると言います。東京湾で練り船を出してくれる船宿さんは少なくなりましたが、ぜひチャレンジしていただきたい釣り方です。

練り船による運河でのハゼ釣り
海に出た落ちハゼをねらう船釣りでは、船も大型になっていき、動力船である遊漁船が使われます。船長さんが、広い海の中から、当日の様子に合わせて釣れるポイントに連れて行ってくれます。遊漁船の多くは、とも(船の後ろ側)にスパンカーと呼ばれるほを上げて潮の流れと風を使って船を安定させています。釣り場に着いたら船長さんからの合図を待ってハゼ釣り開始です。設備のある船では、釣ったハゼをその場であげる「天ぷら船」をしてくれる場合もあります。

昭和30年代のハゼ釣り船(東京湾葛西沖:三枚洲、写真:澤田氏提供)
最近では、そうした天ぷら船の発展形として、屋形船でハゼ釣りということも行われています。屋形船は大型ものが多いので、入れる運河や海域は限られてしまいますが、多くの船宿さんでは、釣り具なども用意してくれますし、何より、釣り船に乗るときのような重装備は必要ありません。江戸の粋(いき)な遊びである屋形船と釣りを合わせた新たな楽しみ方として注目されています。
>

屋形船での釣り(朝潮運河のハゼ釣り調査、2011年)
間もなく今年のハゼ釣りシーズンがやってきます。2020年度の調査結果を見ると、場所によっては、早い時期にヒネハゼが釣れる可能性があるようです。様々な釣り方へもぜひチャレンジしてみてください。ハゼ釣り、楽しんでまいりましょう。
>
執筆:古川恵太(NPO法人海辺づくり研究会・(一財)東京水産振興会)

朝潮運河いきものルネサンス
朝潮運河いきものルネサンスの活動を紹介します。